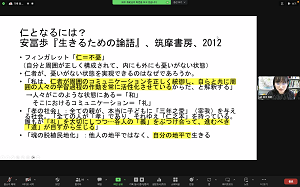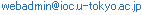News
2023年度 第5回 定例研究会 「選択からの自由」 安冨 歩 元教授 最終研究発表会が開催されました
報告
■はじめに
アメリカの哲学者フィンガレットは、その著書 Confucius: The Secular as Sacred において、『論語』の道が分岐しないことを見出し、それが「西洋人」にとって驚きであることを指摘した。倫理というテーマで「道」とくれば、必ずや「分岐」しているはずで、そこでどの道を進むべきかという決断を下すことになる、というのである。
フィンガレットの驚きは、私にとって、驚きであり、なぜこのような概念にとらわれているのか、知りたいと考え、折に触れて文献を見繕ってきた。最終研究発表会では、この概念の起源をたどるための、初歩的な試みを行なった。以下がその概要を後からまとめたものである。
▪️ヘラクレスの「分岐点」
ギリシャ神話のヘラクレスの物語には、選択らしき話が出てくる。クセノフォンの『思い出』というソクラテスを描くドラマのなかで、この場面が語られる。思春期に、これからどういう風に生きていこうか、と考えていると、<幸福>あるいは<悪徳>の女神と、<徳>の女神がやってきて、それぞれ自分の方に来るように誘惑する。ただ、そこでは、「選択」という言葉は使われていない。
この物語が、選択のひとつの起源のようである。河合祥一郎『謎解き『ハムレット』: 名作のあかし 』(ちくま学芸文庫 2016)によれば、中世西欧の知識人は、みんなこの物語を知っており、シェイクスピアの『ハムレット』の"To be, or not to be" という選択の独白も、これを踏まえている、という。
▪️アリストテレスの「プロアイレシス」
「選択」という概念を明確にしたのは、アリストテレスである。金井寿男「アリストテレスにおけるプロアイレシス論(1):その生成の地平」(『静岡女子大学研究紀要』 (9), p23-36, 1975)によれば、この言葉は、日常語としても使用頻度が低く、プラトンも一度しか使っていない。学術的概念として深い意味が与えられたのは、『ニコマコス倫理学』と呼ばれる書物においてである。
プロアイレシスとは、目標を達成するために理性にもとづいた熟慮の末に、自分に可能な行為や取りうる手段を意図すること、だと言ってよかろう。この概念は衝動的な欲求と対立しており、それを抑えるものである。熟慮の末に良き選択を重ね、それを習慣(ハビトゥス)として確立し、高潔な人格を形成する、というのが高次の目的である。それゆえ。この概念は、責任と深く結びついていたが、「自由 エレウテリア」とは無関係であった。
▪️ストア派
ギリシャおよびローマで有力てあったストア派において「自由」は「幸福」とともに「知者」のみが達しうる理想的なあり方とされていた。「知者」とは,人間が到達しうる理想的な境地を人格化した概念である。このような「自由」は,「自分が欲するとおりに行為する/生きる権能」と規定される。(近藤智彦「ストア派は内面的な幸福を説いたか」『哲学の探求』第 42 号 哲学若手研究者フォーラム 2015 年 4 月 (2-23))
ストア派の代表的哲人であるエピクテトスは、アリストテレスの著作から学んだとは考えにくいが、何らかの形でそれを継承し、プロアイレシスを特に重視した。しかしその範囲をずっと限定的に捉える。
彼は、外的な状況を自分の意志で変更することはできないし、内的な情念も自分の思いのままにはならないと見る。かくて、自分の理性的な部分のみがプロアイレイシスの範囲だということになった。
エピクテトスは、奴隷の出身とされており、その出自のゆえか「自分の実現できること」という範囲を極端なまでに狭く設定し、他人が決して介在することのできない自分の内面に限定するばかりか、自分の精神の自由を守るため、その尊厳を守ることができない状況に追い込まれたなら、従容として自ら命を断つべきであると考え、そこにプロアイレイシスの基礎を置いた。このように、自らの選択しうる範囲を合理的に認識することで、自由へと到達しうる、と考えるのである。言うまでもないが、この「自由」は、「自由意志」とは無関係である。
▪️オリゲネス
ストア派のプロアイレシスの概念が、最初のキリスト教理論家とされるオリゲネスに影響を与えた。オリゲネスは、もし神が全てを決定し、人間に何も委ねていないのであれば、人間の行為の良し悪しが、最後の審判における救いや滅びと無関係になってしまう上に、この世の悪を神が創造したことになってしまうと案じた。そして、このような決定論的で運命論的な考えを、異端として鋭く排除した。
オリゲネスは、「人間の内に在るこの理性は、本性上善悪を識別する能力を有しており、それを判別した時に承認したことを選ぶ能力を持っている」(『諸原理について』III.1.3)とし、人は自らの行為に重い責任を負っている、としたのである。もちろん、人間には、それを全うする能力に欠けているが、神の恩寵により、自ら良き選択を維持しようちする者は、そうすることが可能となる、という。
ここで、選ぶ能力、と言う言葉はラテン語で、facultas ctiam eligendí となっている。オリゲネスの選択は、一時的なものではなく、そのような姿勢を維持することで人は成長し、救済に近づく、と考えていたようなので、そこがアリストテレスと共通してはいる。それでも、選択が、原罪や最後の審判という物語と結びついた点が重要である。(久山道彦「オリゲネス『原理論』における悪の問題序論」『基督教学研究』 巻10 、127〜143頁)
▪️アウグスティヌス
西欧キリスト教の基礎理論を築いたのは、アウグスティヌスとされる。彼は、オリゲネスから深い影響を受けて神学を構築したことが、近年、明らかになっている。オリゲネスは死後300年も経ってから、異端とされたので、その影響関係が、最近まで曖昧になっていた。
その初期の著作『自由意志論』は、「悪はどこから来るのか」についての、マニ教の「物質が悪である」という二元論的回答に反駁するために書かれた。というのも、物質が悪であるなら、それを創造した神も悪になってしまうからである。神が創造したものは全て善であるという一元論に立つなら、そのような議論は受け入れられない。アウグスティヌスは、人間の自由な意志による選択に、悪の根源を見る。悪の原因が人間の自由意志にあればこそ、神は人間を裁くことができる。ここで、選択を、最後の審判と結びつける仕組みが完成した。
▪️「煉獄」
こういう設定の上で、中世西ヨーロッパでは、最後の審判がますます重視され、畏れられるようになる。そうなると、生きている間に犯した罪を、生きている間に贖罪できなかった場合には、死後には何もできない以上、最後の審判で確実に地獄に落とされることになってしまう。それはあまりにも怖いので、アウグスティヌスらが「煉獄」という概念を生み出した。
それは、天国と地獄との間にある世界で、小さな罪を犯した者は、死ぬととりあえずそこに移されて火によって浄化され、罪が焼き尽くされれば、最後の審判を待たず、即座に天国に入れる、というものである。中世に造語された煉獄を意味するラテン語 purgatorium は、purgare〈浄化する〉という意味の動詞に由来する。とはいえ、その浄化の痛みは、この世の如何なる痛みよりも辛く、しかも何百年も続くので、相当に怖い。
そこで、子孫や友人など、縁のある生者が代わりに善根を積み、それを死者に分与することで、煉獄の滞在時間を短縮しうる、ということになった。どうやって善根を積むのかというと、ベストは十字軍に従軍することであるが、巡礼に出たり、教会に寄進するのも有効である。贖宥状というのは、寄進のためのものである。「贖宥状を購入してコインが箱にチャリンと音を立てて入ると霊魂が天国へ飛び上がる」という有名なキャッチフレーズは、死者の霊魂が煉獄から解放されて天国に行ける、という意味である。中世西欧のキリスト教とにとって、こういう善根を積むことが「良き選択」であった。(ジャック・ル=ゴッフ『煉獄の誕生』〈新装版〉 (叢書・ウニベルシタス 236) 2014年)
▪️「怒りの日」
このような贖宥のために、「レクイエム」という死者のためのミサをあげることが奨励されるようになった。もちろん、教会にお金を払ってあげてもらうのである。レクイエムのクライマックスはトマーソ・ダ・チェラノが13世紀に作詞したといわれる「怒りの日 Dies Irae 」という最後の審判を描いた部分である。
そこに以下のような二節がある。(拙訳)
Mors stupebit, et natura, 死神も、母なる自然も、
Cum resurget creatura, 驚かん、死人の起きて、
Iudicanti responsura. 裁き手に、答えんとする。
Liber scriptus proferetur, よろずごと、書き記された、
In quo totum continetur, 書き物の、取りいだされて、
Unde mundus iudicetur. 裁かるる、この世の全て。
responsura というのは、応答する、という意味の動詞であるが、英語で責任を responsibility (応答できること)というのは、ここから来ているのではないだろうか。最後の審判で裁き手のイエスに申しひらきをする、というのは大層重い。しかも、世界のあらゆることが書き記されたデータベースがあって、それをイエスが検索しながら詰問する、というのであるから、言い逃れは無理である。これが「責任」の意味である。
人間に「選択の自由」=「自由意志」がある、という設定は、最後の審判を成り立たせるべく、人間に「責任」を負わせるための罠のようなものである。このような罠に自発的に引っかかる必要はない。
▪️イスラーム神学
7世紀に成立したイスラームは、後発性利得を活用して、急速にその神学を発展させた。「神の子」のような厄介な存在がなく、論理構成が明快である上に、キリスト教圏で忘れられていた、アリストテレスの講義研究文献を翻訳・吸収したことで、その議論は大きく前進した。
イスラームは、基本的に厳格な予定説をとっており、全てはアッラーの差配ということになっている。にもかかわらず、人間には選択の能力が与えられており、その行為のデータベースに従って最後の審判が下される。
この部分をどう解釈するか、によって、いくつかの流派に分かれている。純粋な予定説から、人間の意思決定の自由を「行為の創造」という形で認め、神にならぶ創造者とする説まで豊富に揃っている。(井筒俊彦『イスラーム思想史』中公文庫、2005年)
12〜13世紀にアリストテレスの著作がアラビア語からラテン語に翻訳され、西欧世界に絶大な影響を与えた。このとき、当然ながら、イスラームの神学が共に流入したはずであり、それがその後の西欧神学の展開の方向性を決定したものと考えられる。
▪️アクィナス
このイスラームの影響下に、アリストテレスの学説を活用して神学を再構成したのが、トマス・アクィナスである。トマスの選択理論は、アリストテレスを直接参照しているが、それでも、力点は異なる。
なにより、トマスの選択理論は、自由意志に結び付けられている。アウグスティヌス的な自由意志のなかに、アリストテレス的な選択構造を位置づけたのであるから、そうなるのは当然である。選択の能力としての自由意思は、理性に秩序づけられているが、理性に従属しているわけではない。理性が提示することを、意思は拒絶することもできる、というのである。(稲垣良典「習慣と意志 : トマスの意志概念の一考察」哲學年報. 34, pp.1-23, 1975年)
▪️ルター
このような「自由意志」によって課せられた責任を、人間が果たすことは不可能だ、と考えたのが、ルターであった。彼が学んだ神学は、アクィナスを批判して、人間の意思をより重視するオッカム流のものであり、責任の重さがより大きくなっていた。(金子晴勇気「ルターとオッカム主義の伝統」『哲学研究』第547号、60-98頁、1983年)
ルターは人間に自由意志がない、というのではなく、そんなものは、最後の審判では、まったく役に立たない、と言うのである。それゆえ、贖宥状を買う、といった良き選択をしても、なんの効果もない、ということになる。これが彼の批判の主眼であり、人間の作り出した教会に献金することで、人間の救済についての神の予定を変更できるなど、ありえないことである。それゆえ、煉獄の概念もまた否定される。ちなみに、予定説で煉獄なし、というのは、イスラームの神学の基本である。
▪️ホッブズ
この人間の選択についての無能力という考えを極北にまで推し進めたのが、ホッブズである。ホッブズは、人間の意思決定など、動物と何ら変わるものではなく、ただ複雑なだけだ、と考えた。
これは、いわゆる機械論であり、こうなると、選択もまた複雑な自動過程に過ぎなくなる。そして、これ以降、現代に至るまで、この考えが基本となっている。もちろん、人間の自由意志を守ろうとする主張は、16世紀半ばのトレント公会議以降、繰り返されているが、それは、そうでなければ「責任」を守ることができず、それでは社会秩序を守れないではないか、という危惧から行われる、一矢報いる、という動きに過ぎない。(トーマス・ピンク『自由意志』 岩波書店、2017年)
▪️選択の無意味さ
「選択=自由意志=責任」という思想は、「最後の審判」という装置を機能させるために必要とされてきたに過ぎない。それゆえ、最後の審判がどうでもよいのであれば、そもそも意味がない。
「必然か、選択か」という問題設定も、全知全能の神がいなければ、意味がない。しかも、量子力学によってミクロな世界に普遍的に偶然があることが示されており、また、マクロな世界においても、不規則遷移現象論(いわゆる決定論的カオス)の発見により、非線形性を含むこの世界には、決定論に従うシステムにも、不可避的に偶然性が現れることが示されている。つまり、決定論的世界にも常に非決定性はあるので、この二項対立も無意味である。
■おわりに
ここで展開したような初歩的概観からでも、以下のことは明らかである。
すなわち、全知全能の神も、煉獄も、最後の審判も、どうでもよいのであれば、選択などという概念は、そもそも不必要である。審判者の前に申しひらきをする責任など、我々にはない。しかも、20世紀の物理学の成果によって、その無意味さは明らかとなった。人間の行為や倫理をこのような概念で考えるのは、不合理である。
ホッブズによって息の根を止められたはずのこの中世的概念が、21世紀の世界で幅を効かせているのは異様である。それはおそらく、国民国家が中世末期に出現したことと関係があろう。人類の直面する差し迫った問題に立ち向かうためにも、オッカムの剃刀によって、不必要な「選択」概念は切り捨てられるべきである。
「選択」に限らず、西欧を起源とするがゆえに近代の帯びる民俗的呪術的諸概念の陥穽を越え、我々の知識をより客観的で科学的なものへと発展させるためには、他の文明で発展した宗教的思想的資源を活用する必要がある。東洋文化の研究は、そのような貢献を果たすべきだと私は考える。
「選択」の穴を埋めるための私の提案は「仁」である。「不仁」が麻痺を意味することから明らかなように、仁とは神経が通っている、という意味がその基礎である。保身のために神経を切って不都合なことから目を背けたりせず、勇気と強さとを維持し、不断に克己して成長を続けることが、その意味だと私は考える。分岐しない「道」は、そのような成長のなかから自ずと現れてくる。(※言うまでもないが、これは「選択」に替わる新しい「選択肢」の提示などではない。)
---当日は、オンライン会場に120名の参加者が集まった。講演後には、コメンテーターや聴衆との質疑応答の中で「魂の脱植民地化」する方法としての「仁」となる方法、古典を向き合いながら根本を考える意義、コミュニティ・組織単位での適用可能性などについて議論が交わされた。
当日の様子
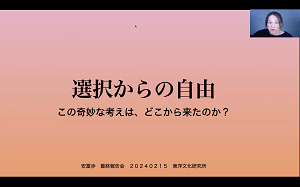 | 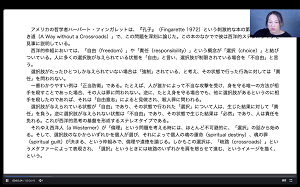 |
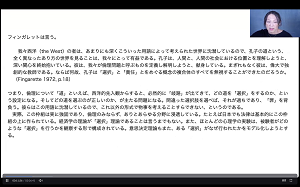 |  |
開催情報
日時: 2024年2月15日(木)14時00分〜16時00分
開催形式:オンライン開催(Zoom)
発表者:安冨 歩(東京大学東洋文化研究所・元教授)
題目:選択からの自由
司会:田中 有紀(東京大学東洋文化研究所・准教授)
討論:長津 十 (ヘルシンキ大学社会科学部実践哲学科・教授)
田中 有紀(東京大学東洋文化研究所・准教授)
使用言語:日本語
要旨:
アメリカの哲学者フィンガレットは、『論語』を研究し、分岐した道のなかから正しい道を選択する、という考えの無いことに気づき、そこに西欧哲学との本質的な差異を見た。『論語』の道は分岐なき道であり、誤りとは、そこから離れてしまうことであって、間違った道を選ぶことではない。私はいくつかの著作で、そもそも、人間が生きる中で、正しい道を可能な選択肢から選択するということは、原理的に不可能なタスクであることを指摘し、現代の諸学、特に経済学を始めとする社会科学は、この選択概念に深く依拠しており、そのことが、これらの議論を不毛にしている、と主張した。では、西欧思想は、なぜかくも深く、選択概念にとらわれるようになったのであろうか。私は、機会あるごとにこの問題を眺めてきたので、最終報告会では、その途中経過を報告したい。大雑把な流れは、以下の通りである。選択の淵源はほぼ間違いなく、アリストテレスのプロアイレシスという概念にあり、それが、さまざまの経路を経て、アウグスティヌスとトマス・アキナスに流れ込み、中世哲学の枠組となった。また黙示録的な最後の審判への恐れが中世を支配し、そこから煉獄という思想が生まれ、そこでの死者の苦悩を削減するためのミサたるレクイエムの重要性が高まった。このような恐怖を背景として、ルターが、人間には選択の能力がそもそもない、という後期アウグスティヌスの主張を徹底し、宗教改革を引き起こした。つまり、選択の自由の否定が、近代を生み出す第一歩となったのである。ゆえに近代哲学は、ホッブズに代表されるような、徹底した選択の自由の否定の方向に進んでいった。 にもかかわらず、近代の社会生活は、選択の自由とそこから生じる責任、という中世的概念を軸に構成され、驚くべきことに、それが現代にまで流れ込んでいる。 それゆえ、現代の諸問題を乗り越えるには、選択からの自由を確保することが不可欠であり、そのための代替概念を探し出すことが、非西欧社会の研究者に求められ、 東洋文化研究はその重要な柱だと私は考えている。私自身が到達した一つの候補は、「仁」である。
登録種別:研究活動記録
登録日時:TueFeb2713:35:152024
登録者 :安冨・キム・多田
掲載期間:20240228 - 20240528
当日期間:20240215 - 20240215